「民俗」と「民族」の意味と違い
「民俗」と「民族」は、同じ読み方でも意味が異なる同音異義語です。
そのニュアンスや使い方には微妙な違いがあるので、混同しないようにそれぞれの意味をしっかりと把握しましょう。
本記事ではその「民俗」と「民族」の意味と違いを深掘りし、用例などを通じて、使い分けのポイントについて解説していきます。
紛らわしい言葉ですが、使い分けることができれば、表現の幅が広がりますので、ぜひ参考にしてみてください。
「民俗」
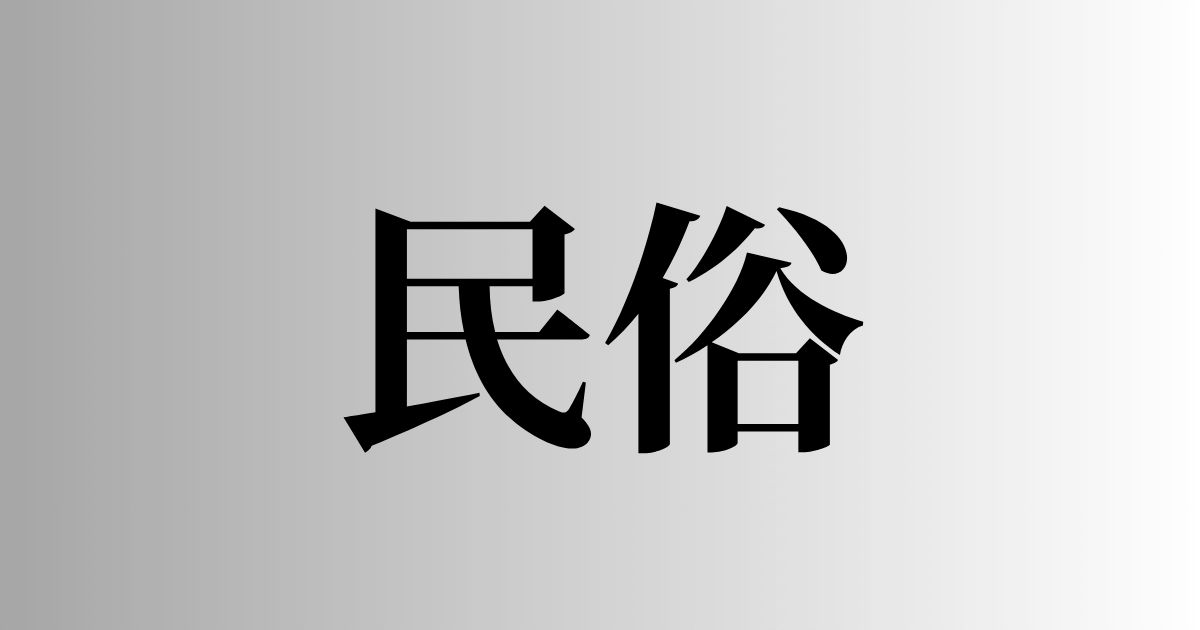
「民俗」は「人々の伝統的な生活文化」「民間に伝承されてきた風俗・習慣」という意味を持ちます。
「民俗」の「民」は「たみ」「ひと」という意味があり、「俗」は「ならわし」「習慣」「世間」という意味があります。
したがって「民俗」は、「民の習慣」すわなち「民間に伝承されてきた風俗・習慣」という意味になります。
「民俗」は「大学では民俗学の研究をしていた」「民俗音楽は奥が深い」「彼は有名な民俗学者だ」のように用いられ、「民俗」の類義語には「土俗」「風習」「因習」「伝統」などが挙げられます。
このように、「民俗」は、民間の生活の中で伝承されてきた習俗・芸能・技術などの総称を指す言葉で、地域によって独特の伝承文化があります。
また、「民俗」は「民俗学」「民俗音楽」「民俗学者」のように何かの言葉とセットで使われることが多いため、「民俗」単体で使われることは少ないです。
「民族」

「民族」は、「出自・言語・文化など共有し、同族意識で結ばれている人々」「文化や出自を共有し、共通の帰属意識を持つ人々の集団」という意味を持ちます。
「民族」の「民」は上述の通り「たみ」「ひと」という意味があり、「族」は「みうち」「なかま」「集まる」という意味があります。
したがって「民族」は、漢字だけで考えると、「ひとのなかま」という意味になります。
しかし実際は、「出自・言語・文化など共有し、同族意識で結ばれている人々」という意味で使われるので、若干の相違がある点に注意が必要です。
「民族」は「伝統的な民族衣装を身にまとっている」「多様な民族で形成されている」「民族の研究は歴史の研究にもつながる」のように用いられ、「民族」の類義語には「種族」「部族」「人種」などが挙げられます。
このように「民族」は、「地域的な起源が同じで、言語や文化などを共有する人々」を指す言葉です。
「民族」は政治的・歴史的に形成されることもあるため、政治や歴史的な状況や背景によってその意味の範囲や捉え方に変化が生じることがあります。
以上のように「民俗」は、「民間に伝承されてきた風俗・習慣」という意味があり、地域によって独特の伝承文化があります。
一方「民族」は「出自・言語・文化など共有し、同族意識で結ばれている人々」という意味があり、政治的・歴史的に形成されることもあるため、状況や背景によってその意味の範囲や捉え方に変化が生じるという点に注意が必要です。
記事の参考文献
- 編 山田忠雄、柴田武、酒井憲二、倉持保男、山田明雄、上野善道、井島正博、笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.
- 著 北原 保雄(2011-2019)『明鏡国語辞典』第二版,大修館書店.
- 編 新村出 (2018,2019)『広辞苑』第七版, 岩波書店.
- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2025年3月5日).
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2025年3月5日).
- 編 一般社団法人共同通信社 (2022). 『記者ハンドブック : 新聞用字用語集』第14版,共同通信社.

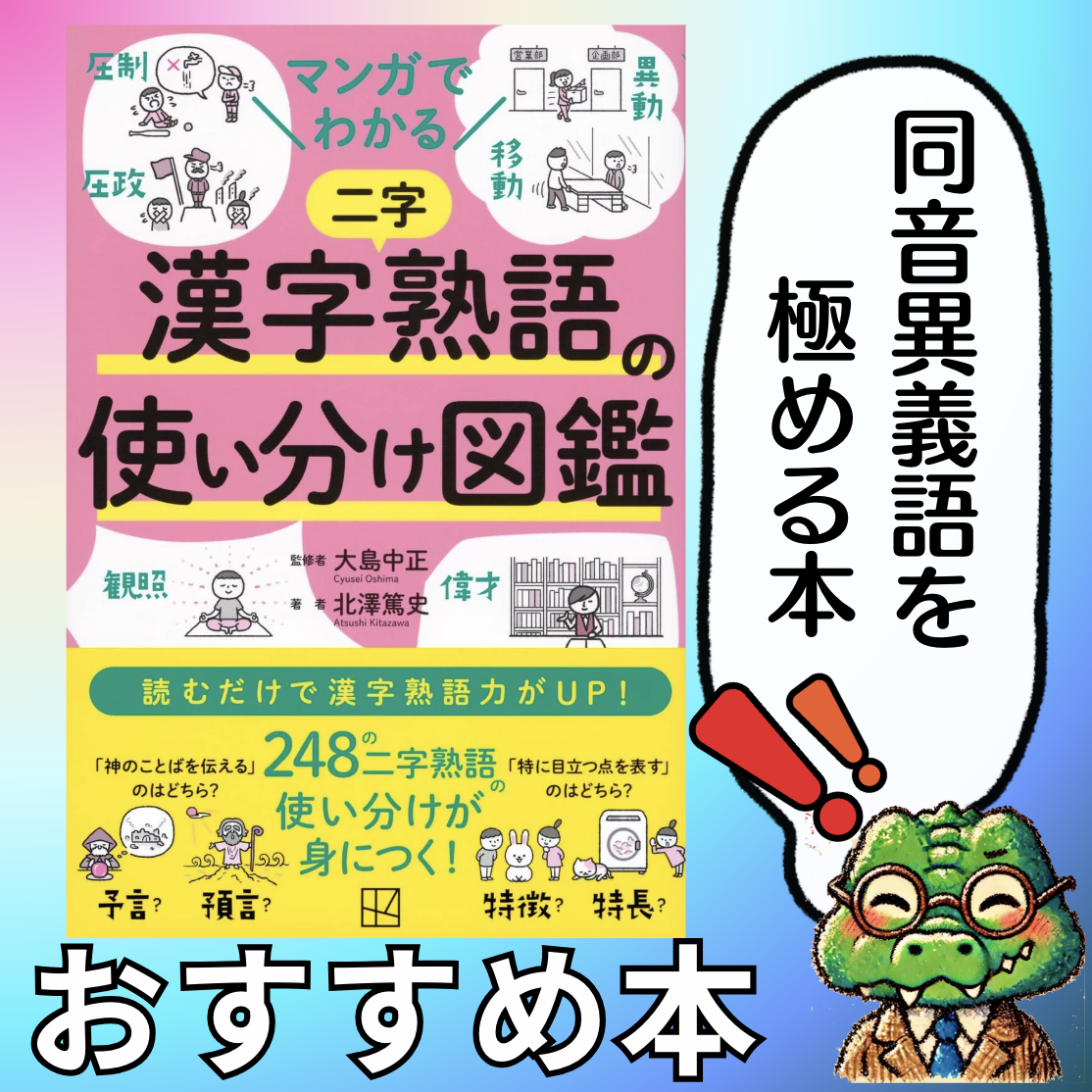
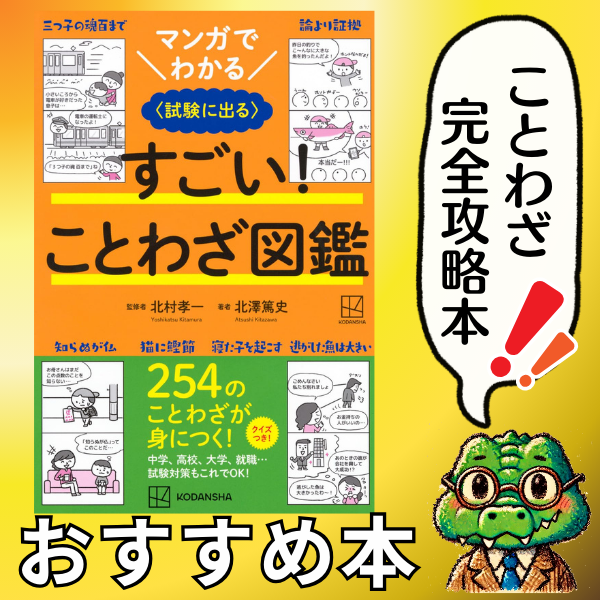
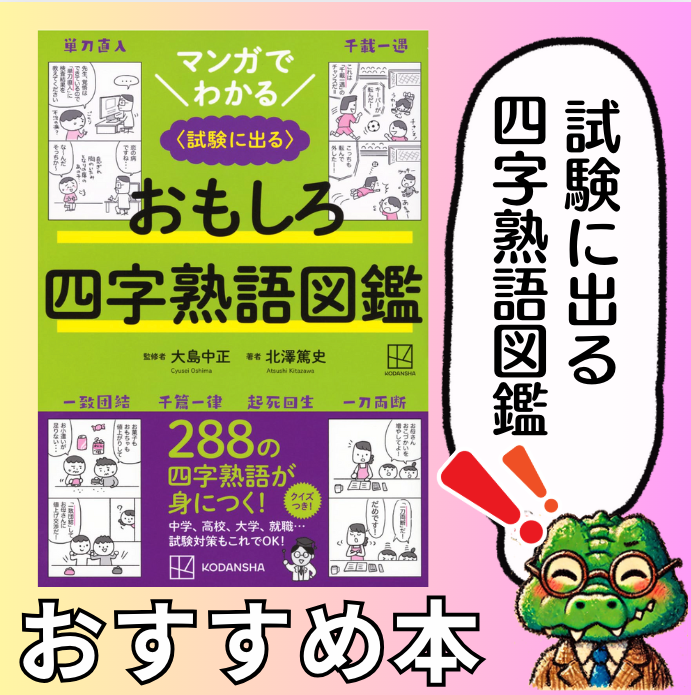
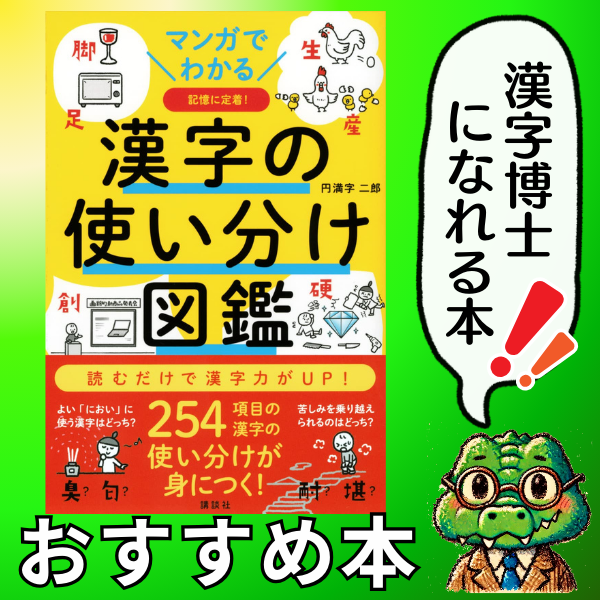
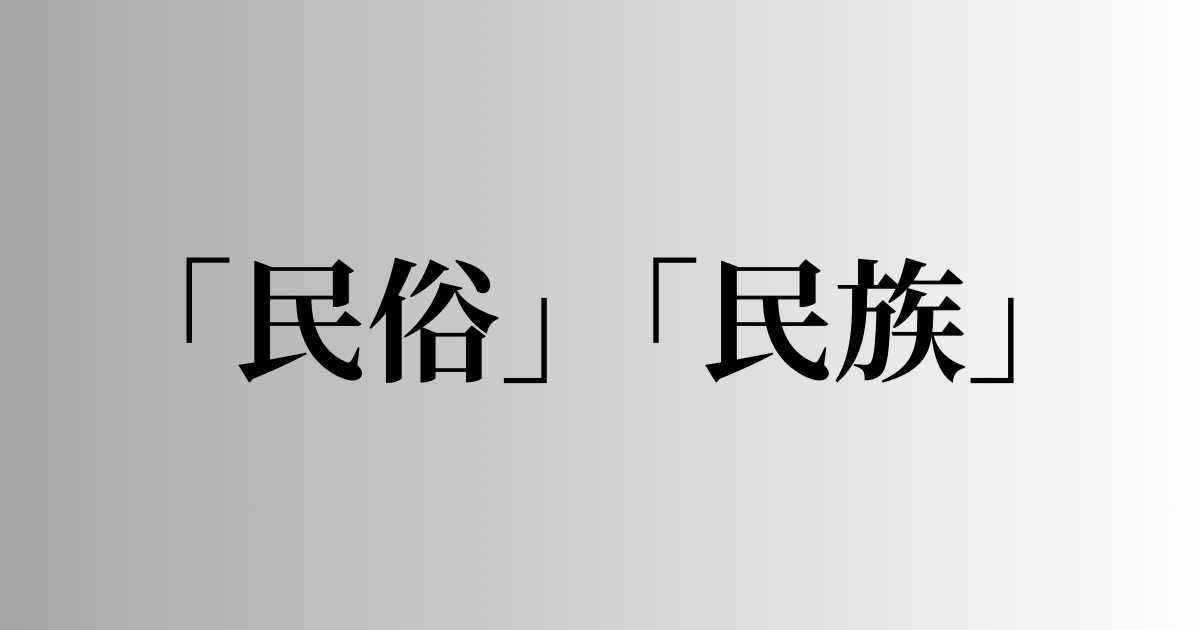
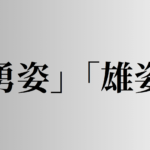
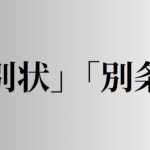
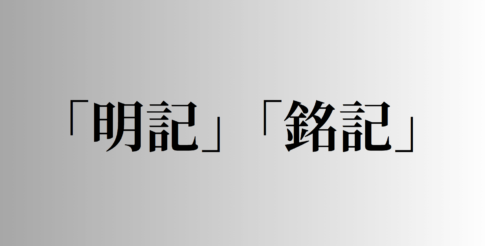

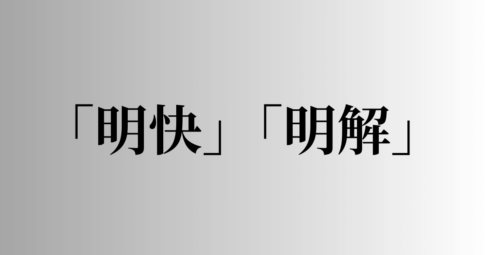

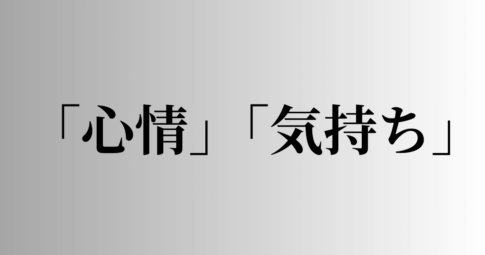
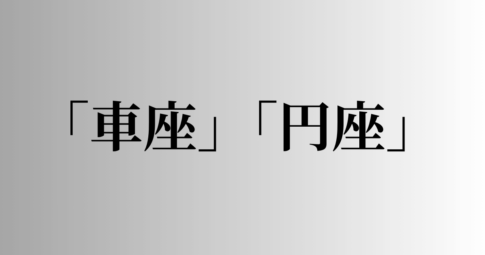
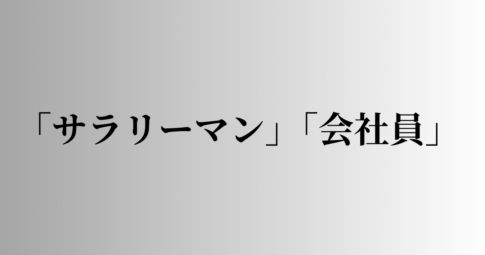
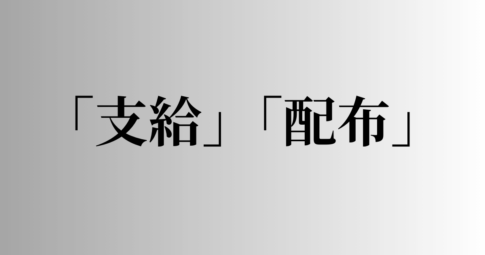
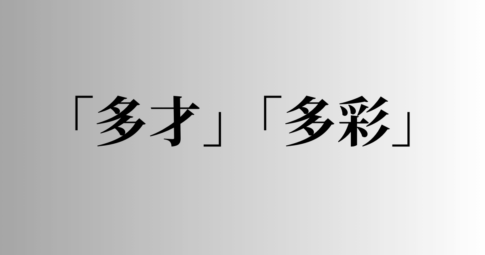


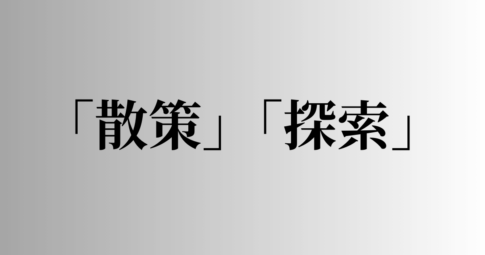




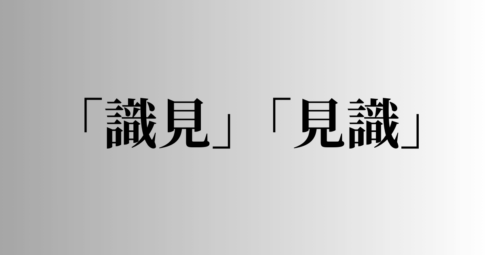
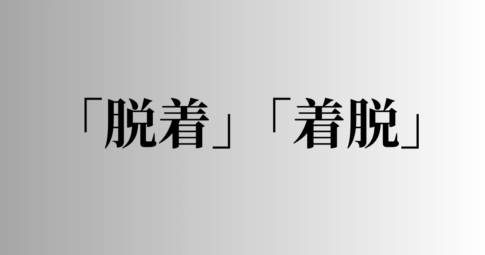

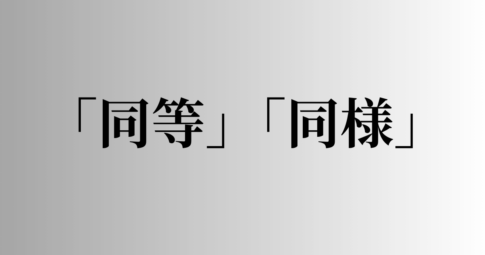

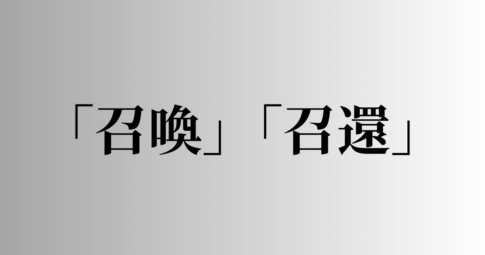

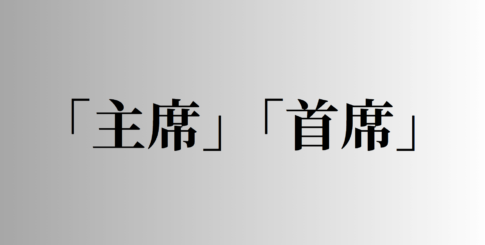
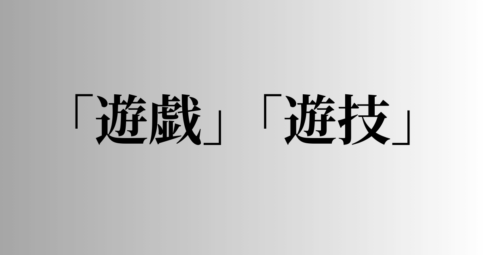
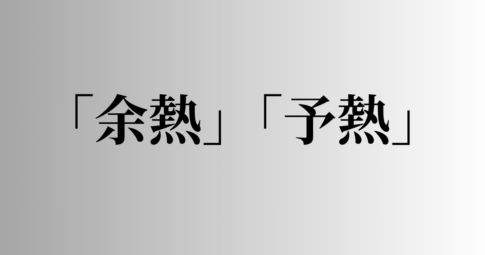
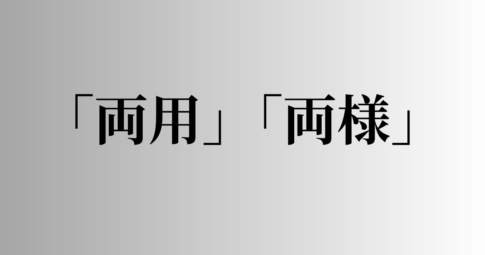
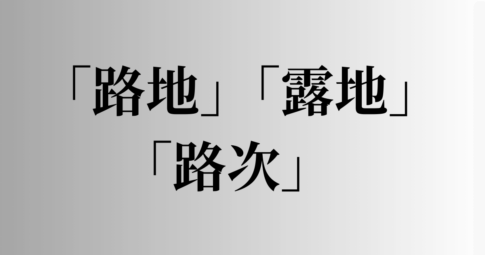
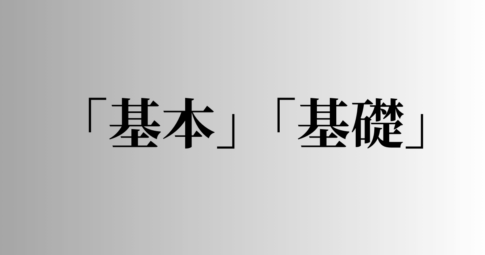
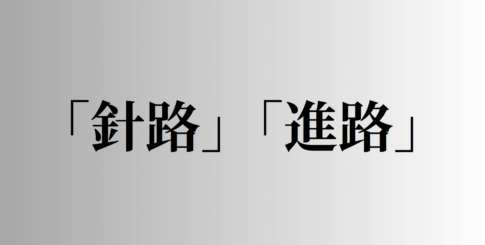
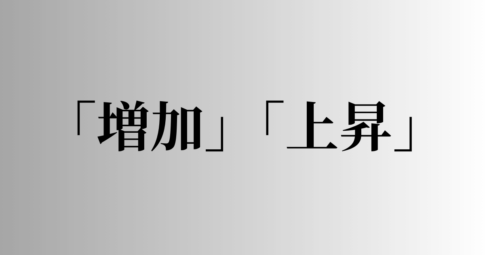
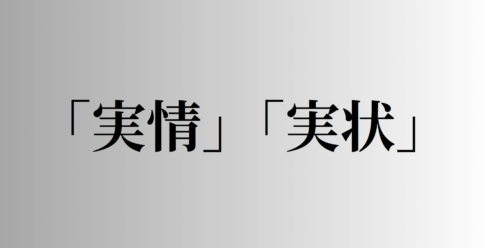
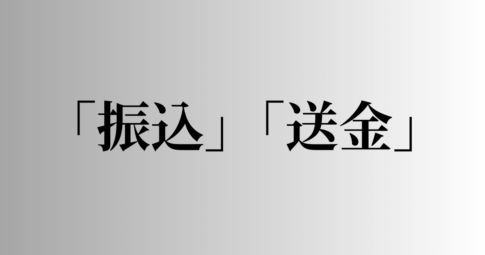

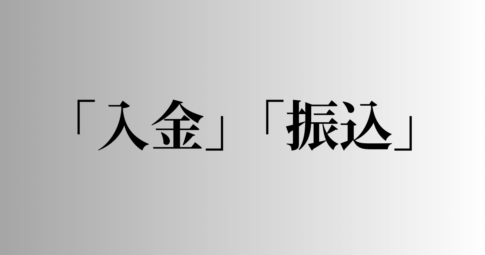
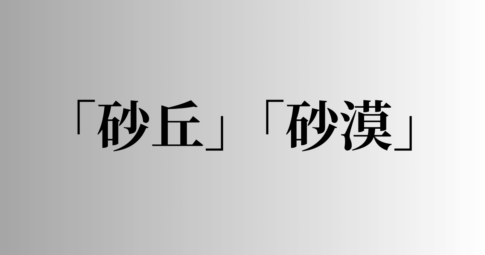
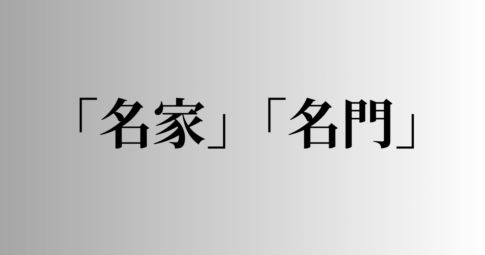
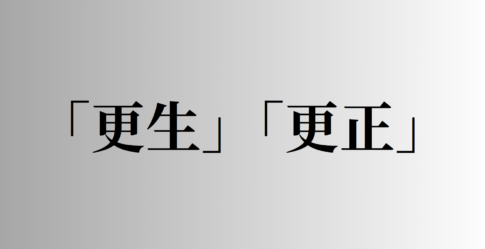
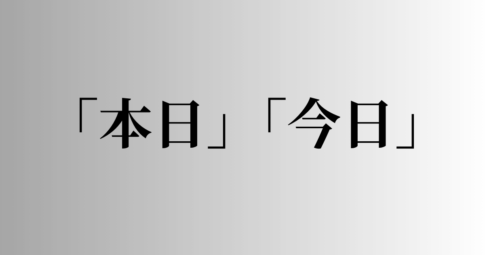

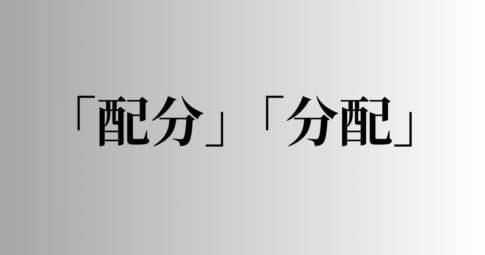
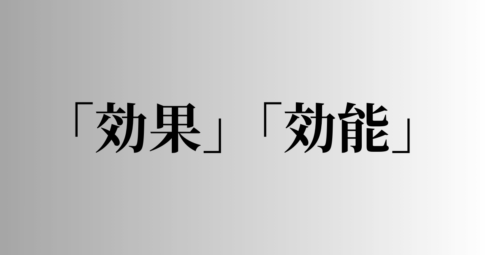
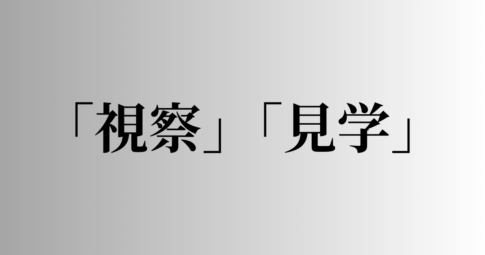
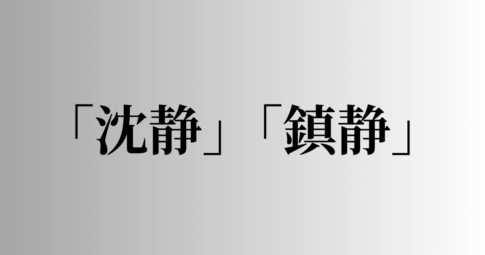
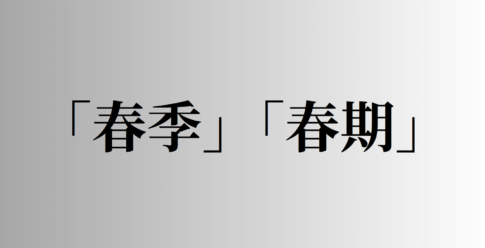
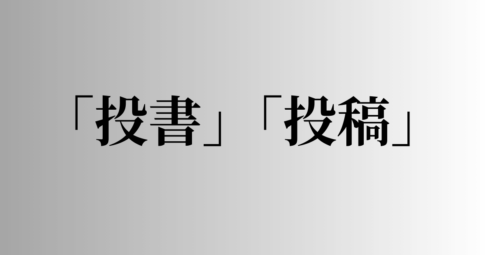

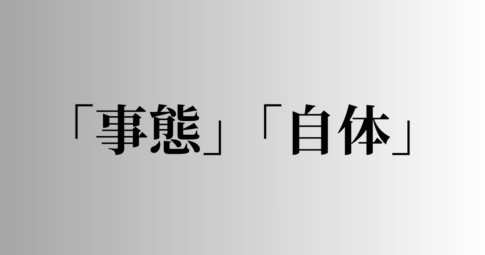
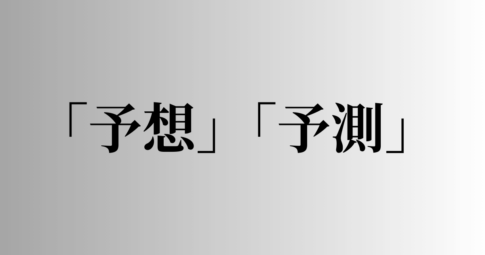
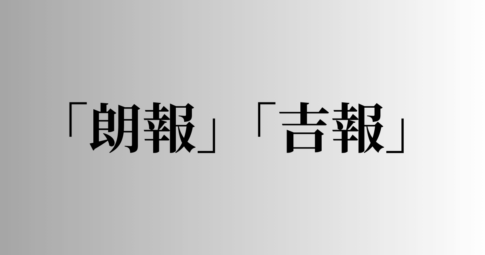
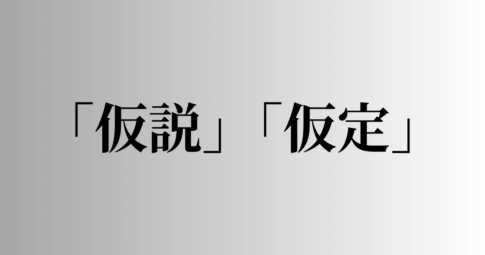
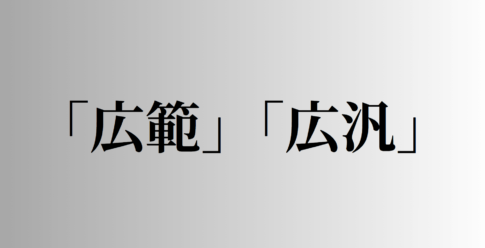
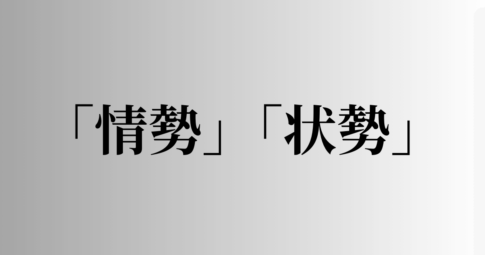
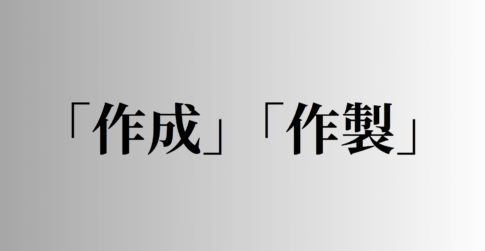
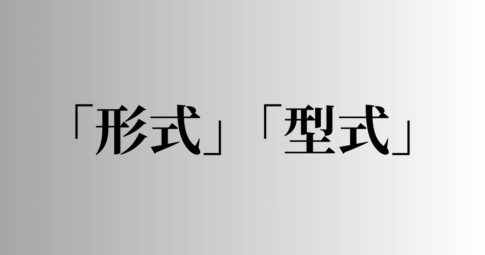
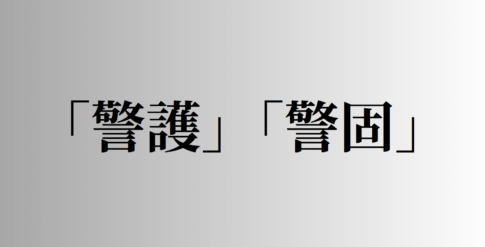
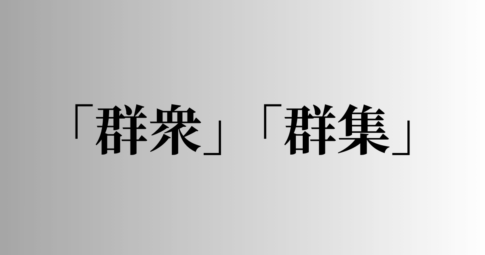

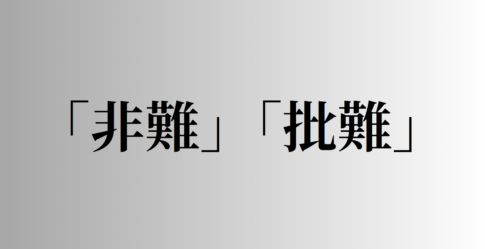
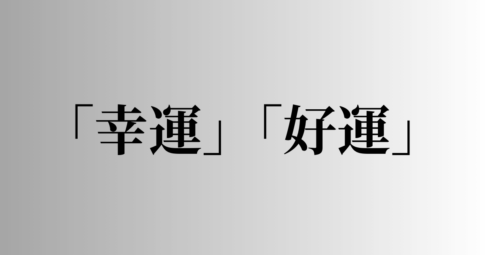

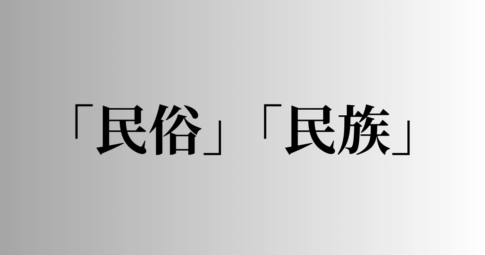
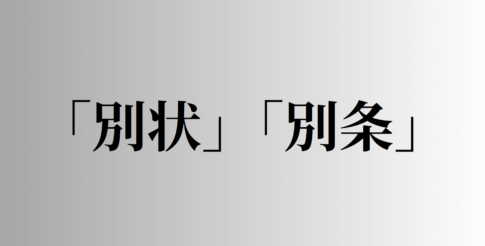
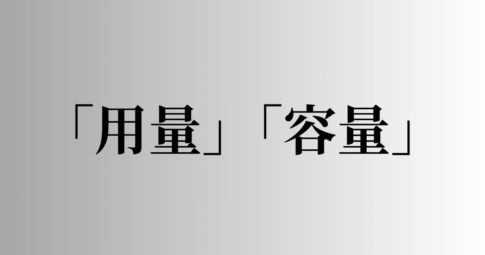
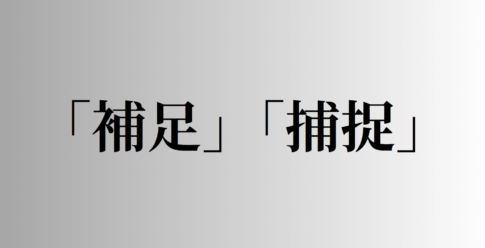
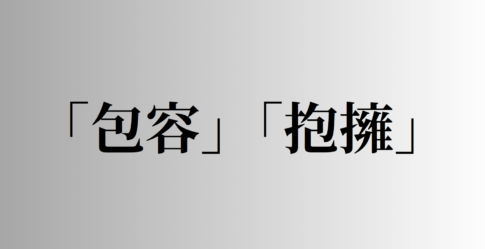

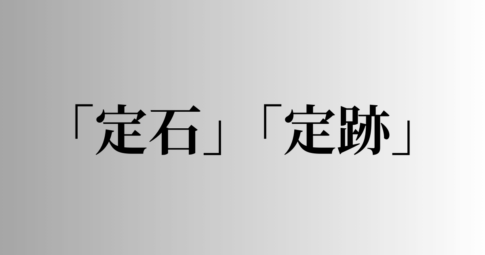

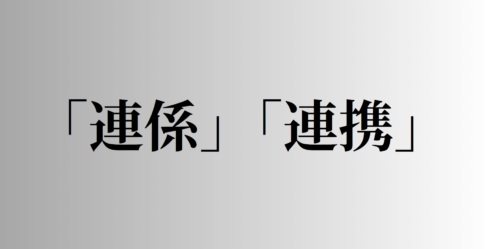
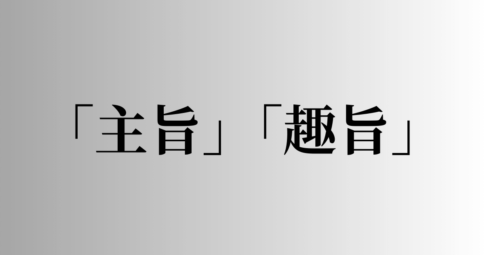

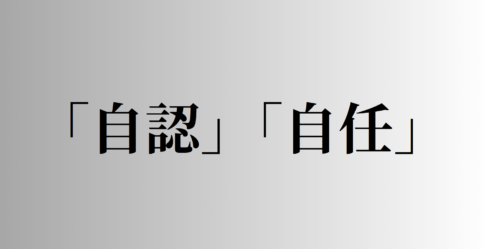
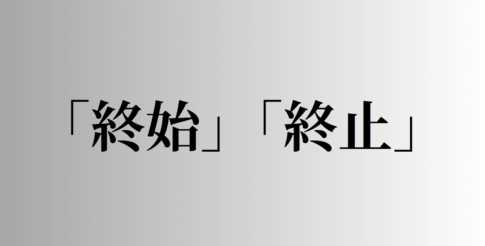
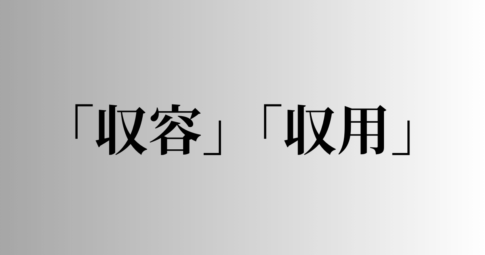
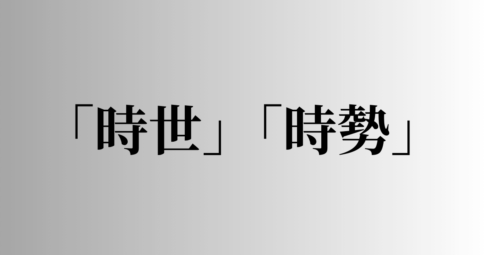
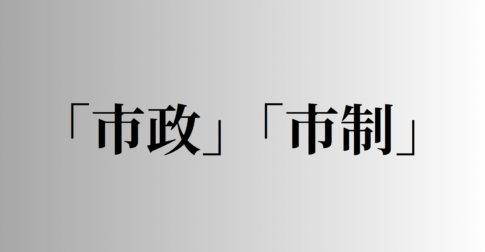
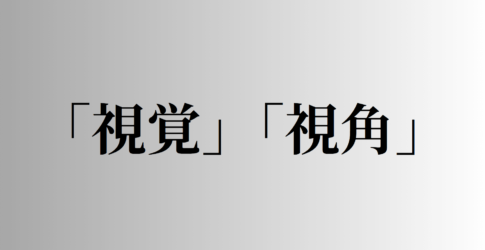
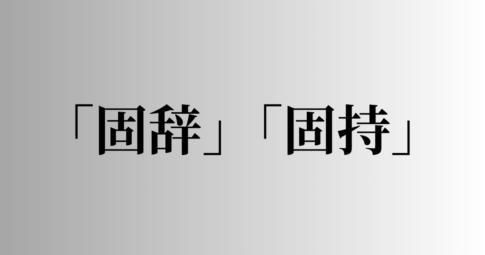
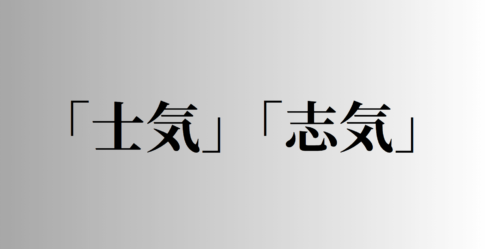
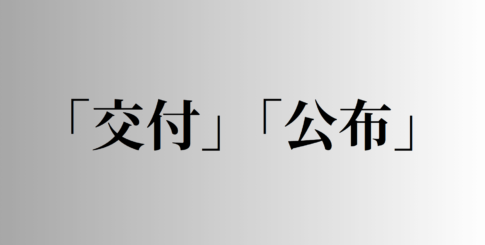
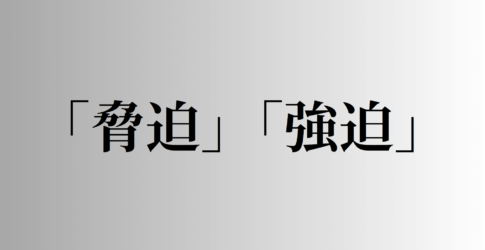
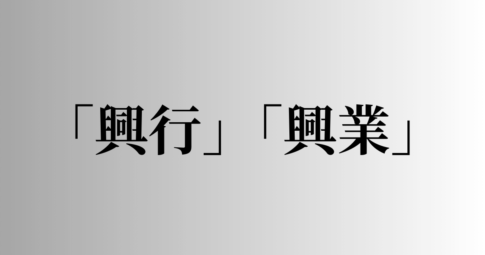
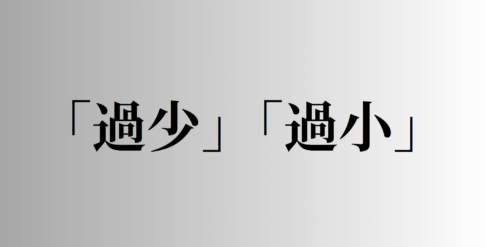
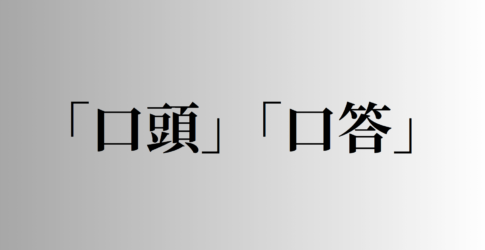
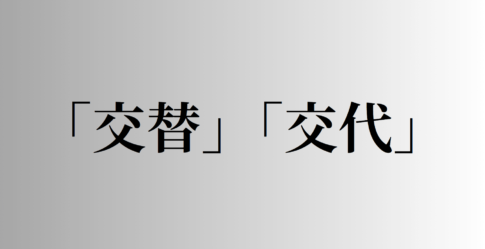

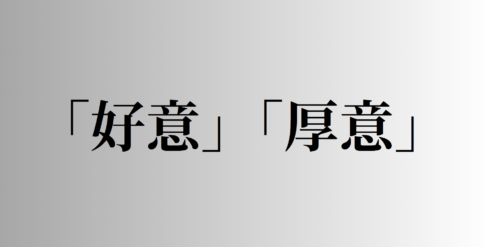
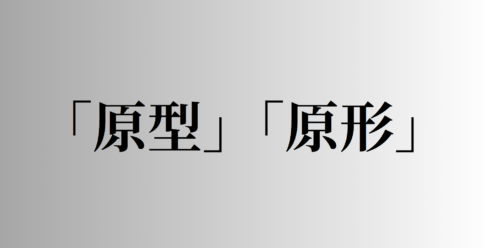
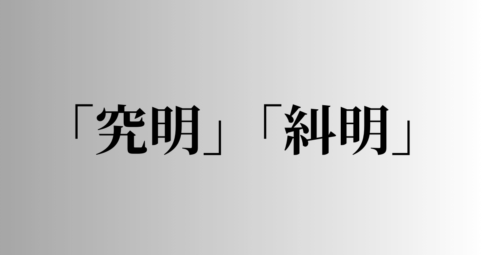
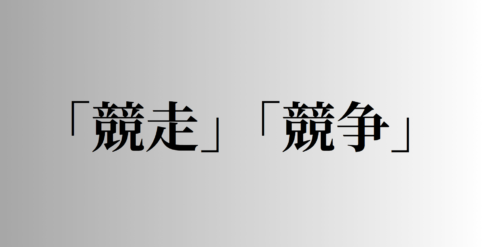
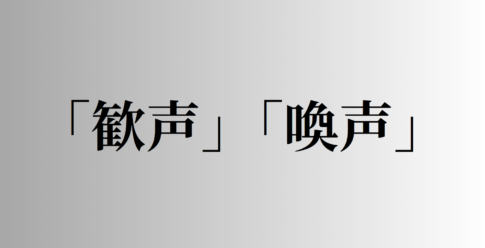
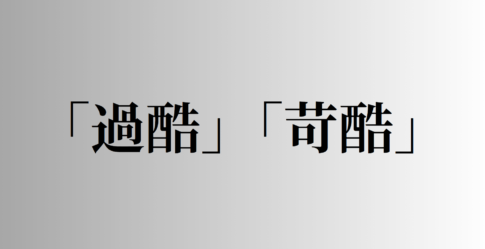
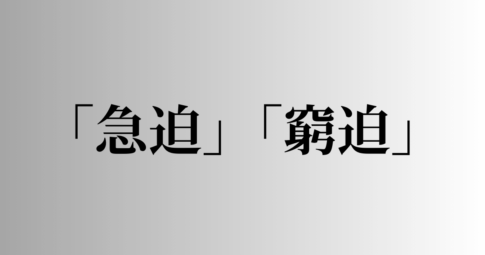
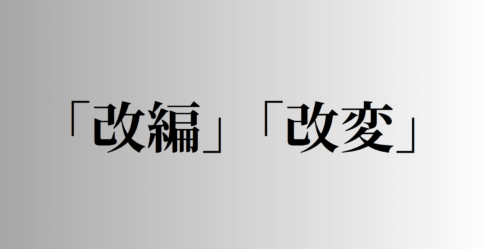
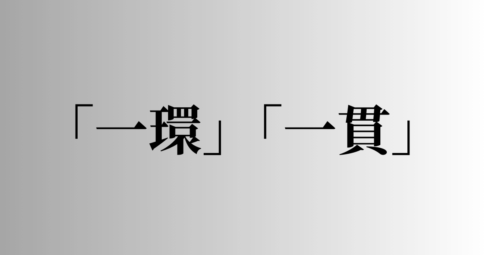

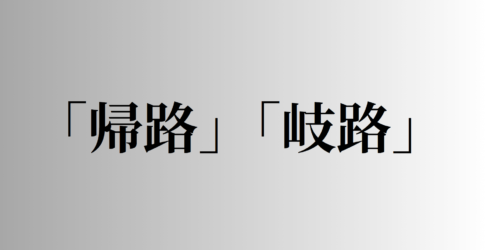

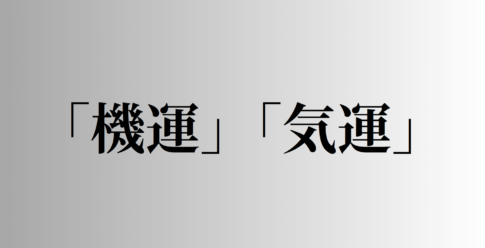
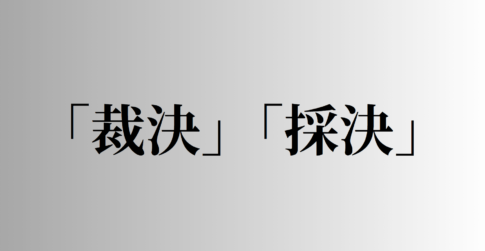
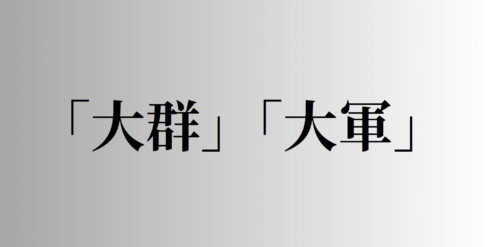
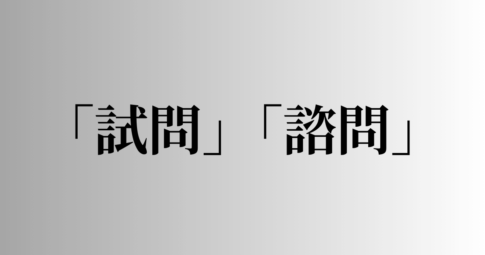
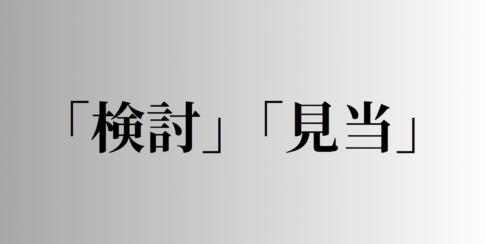
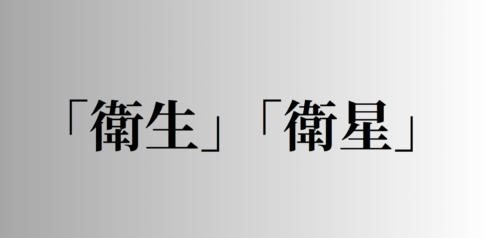
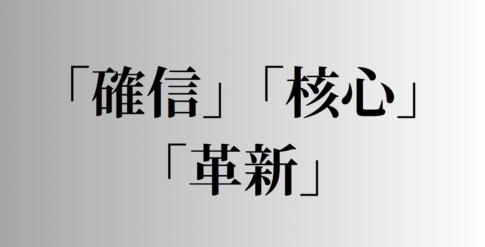
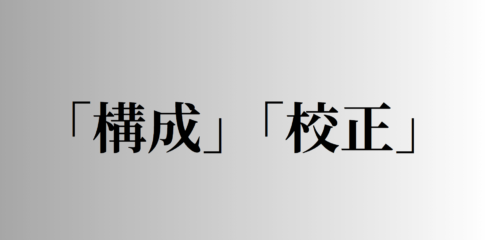
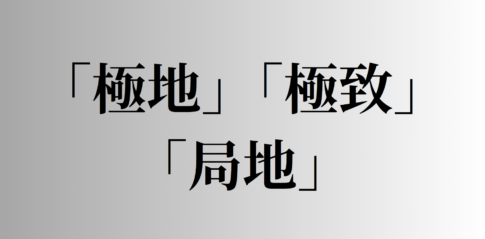
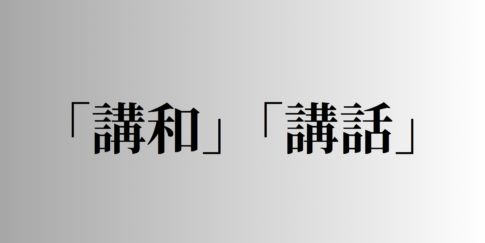
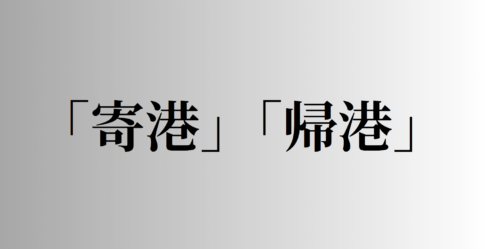
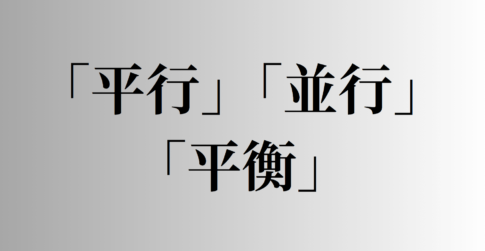
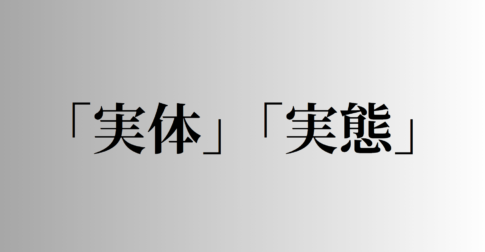
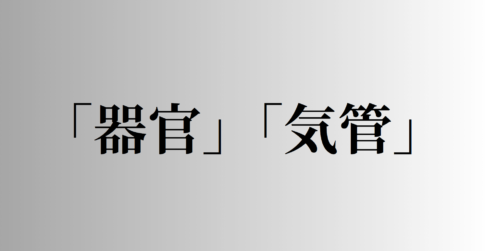
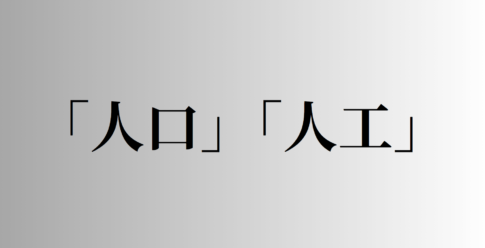
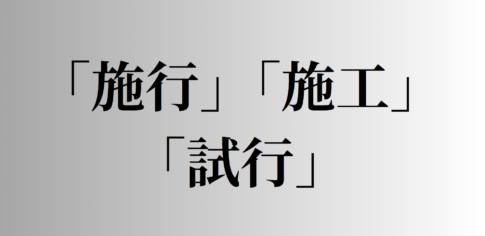
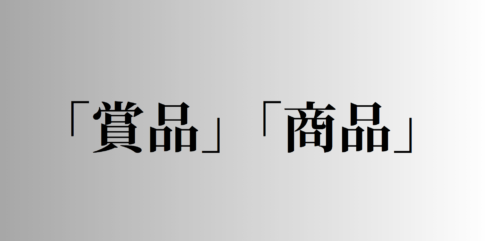
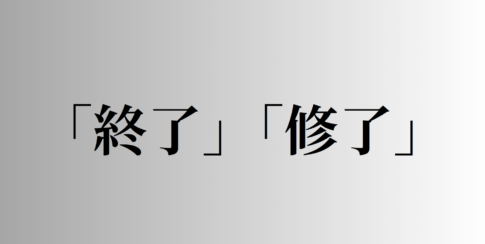

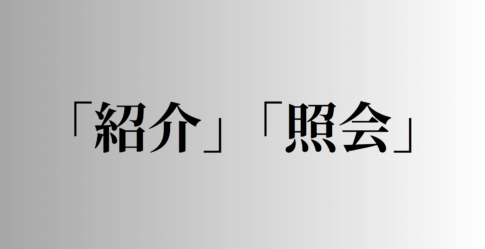

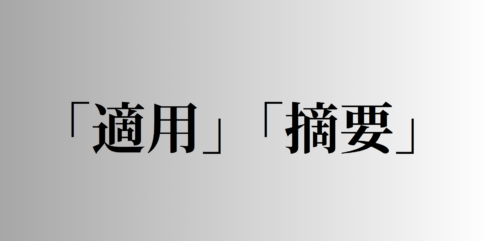
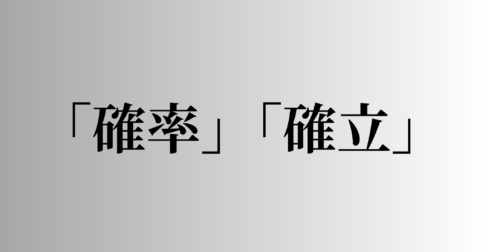
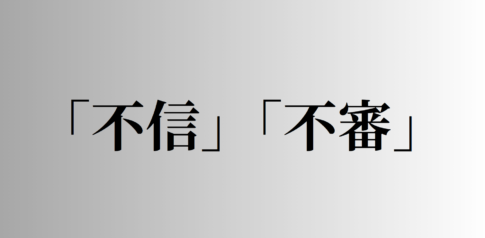
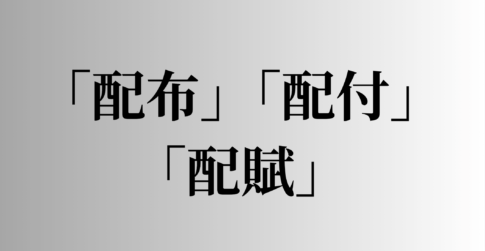
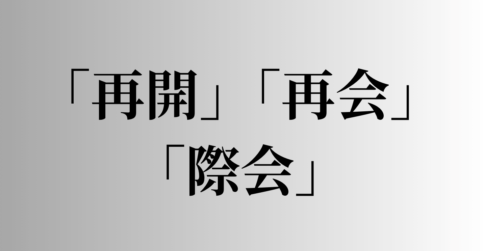
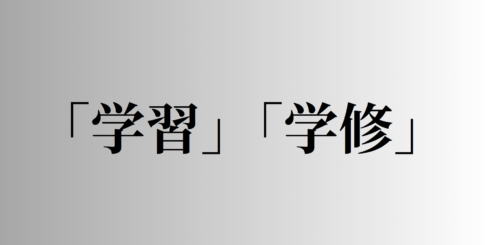
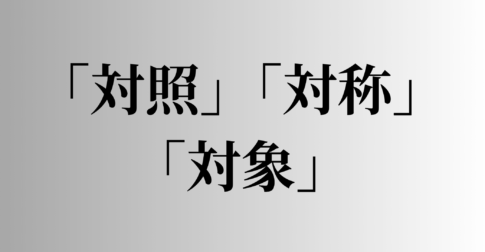
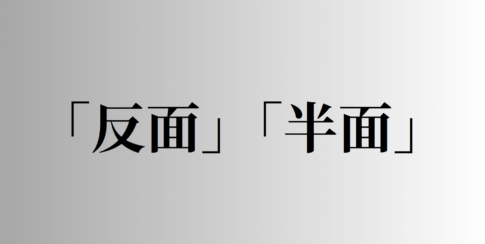
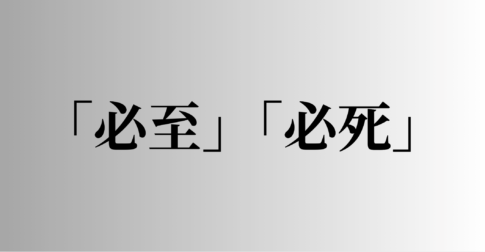
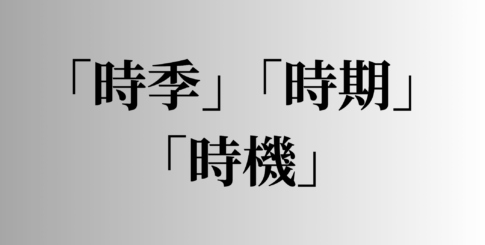

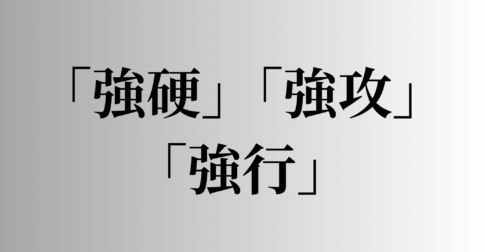
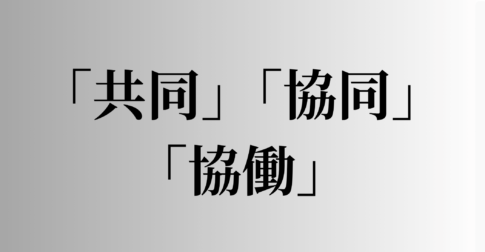
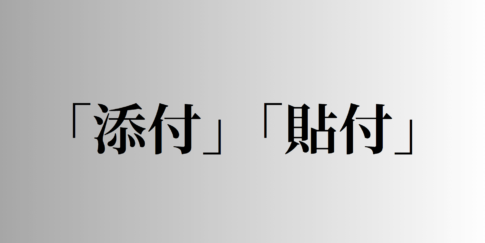
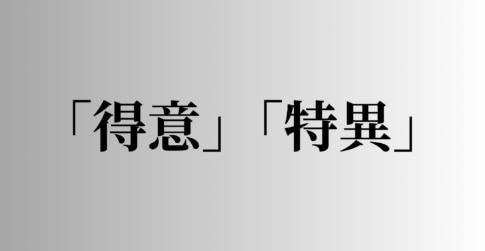
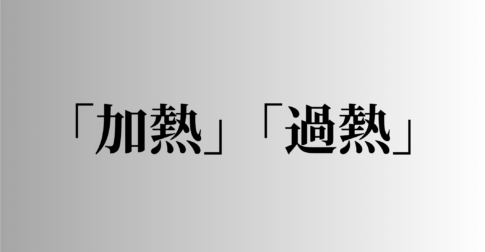
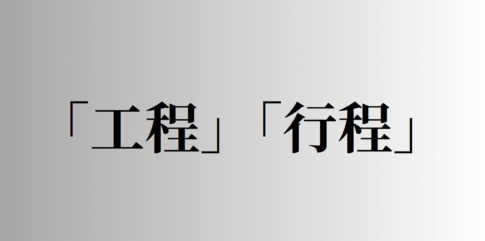
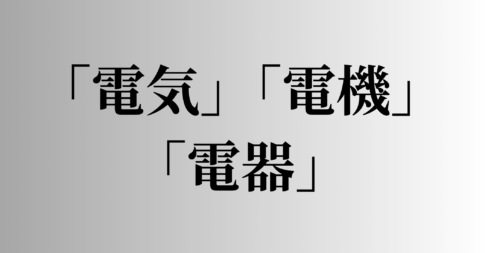
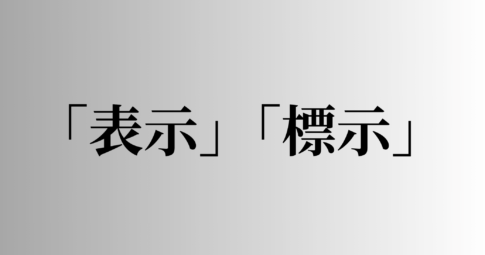
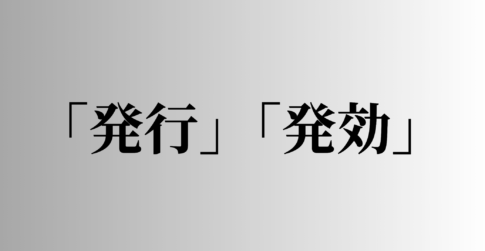
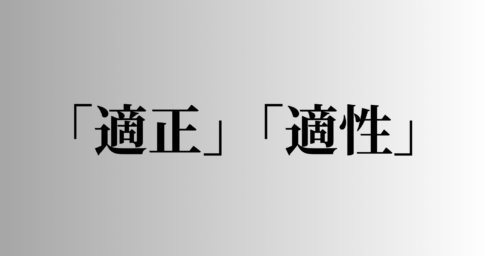
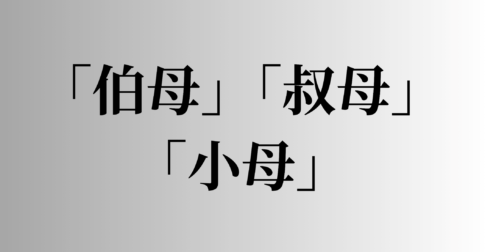
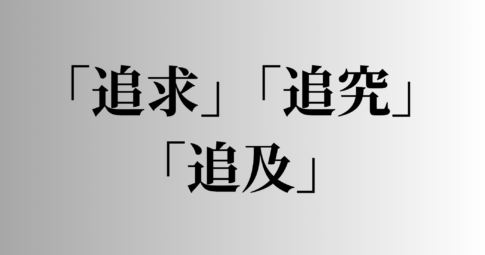
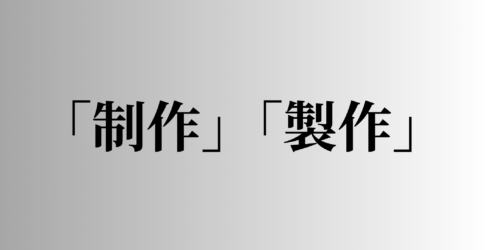
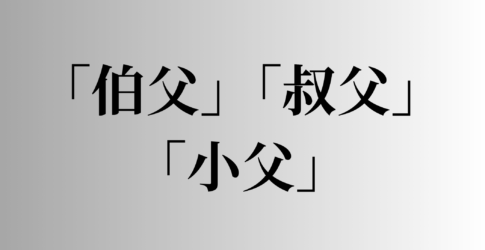
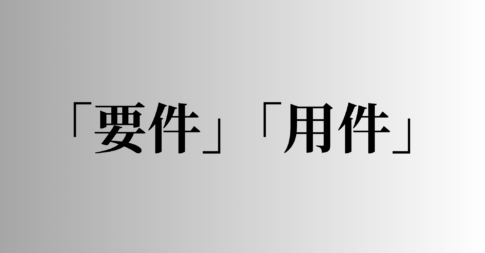
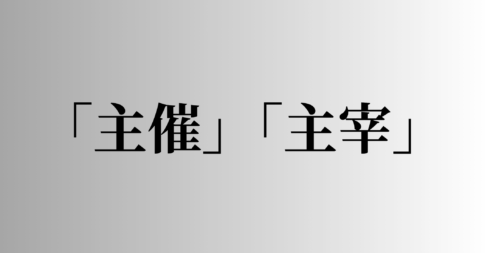
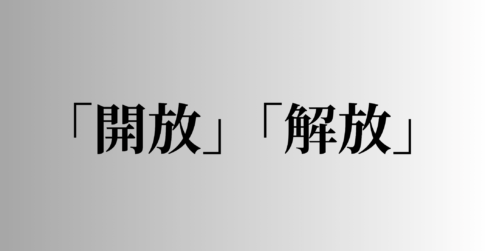
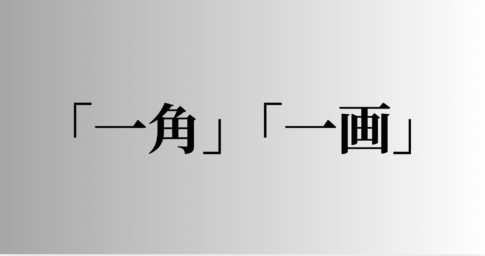
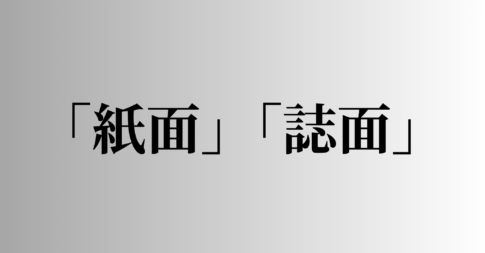
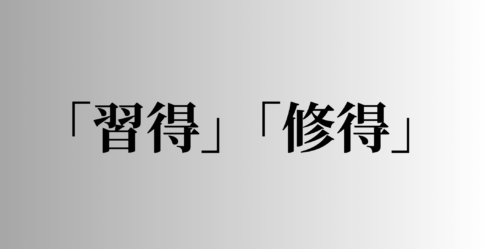
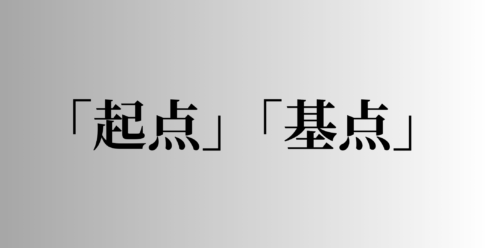
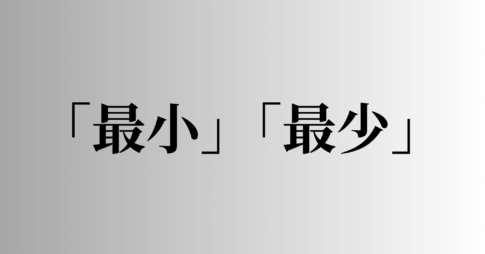
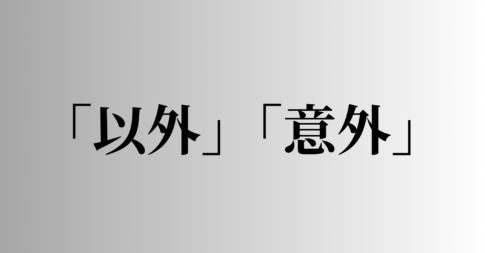
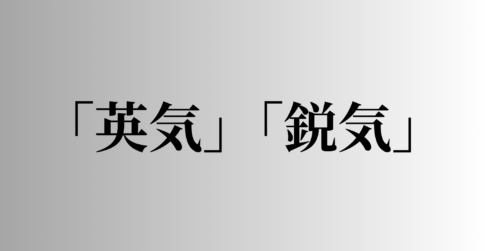
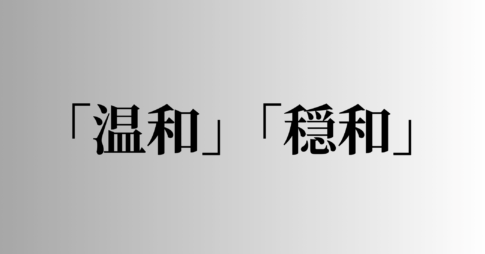
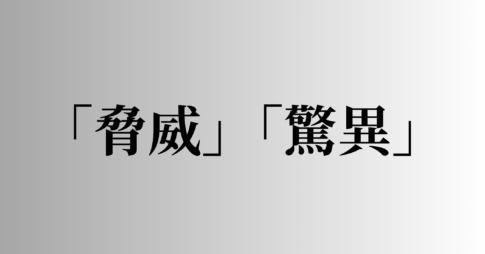
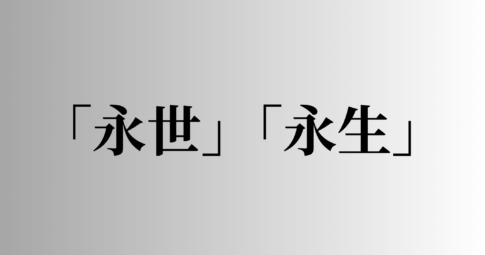
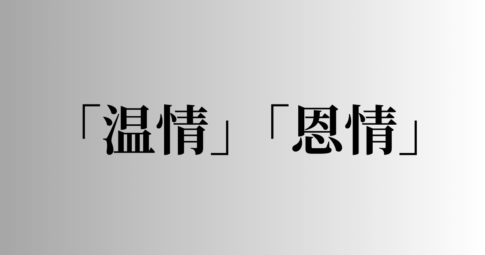
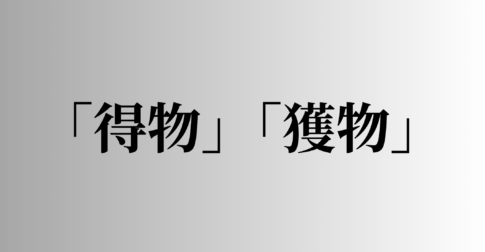
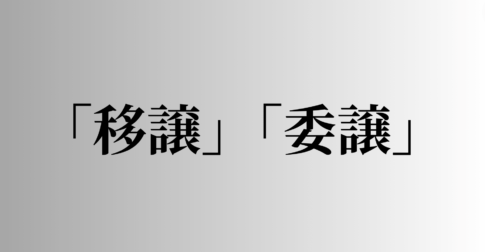
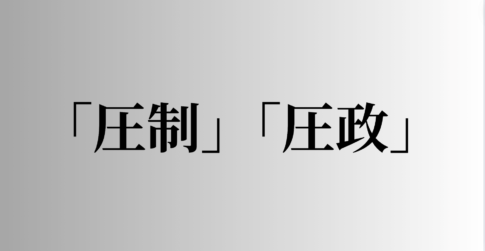
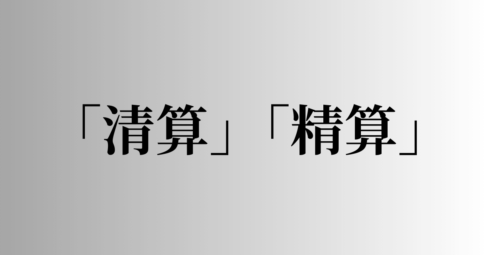
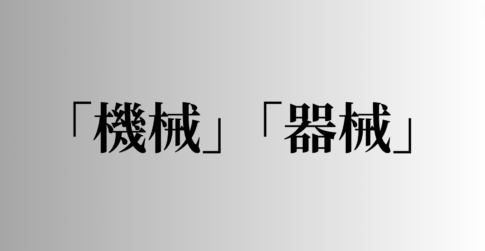
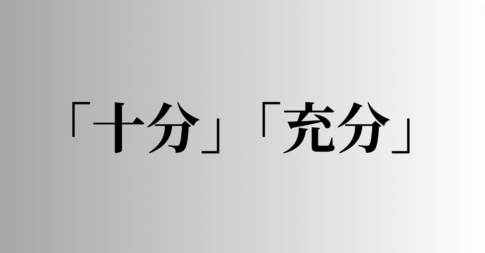

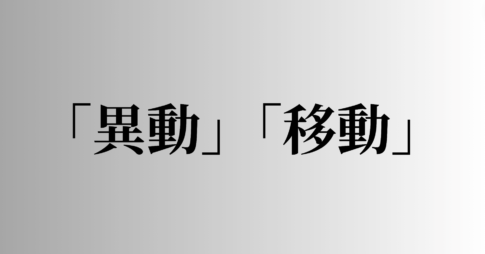
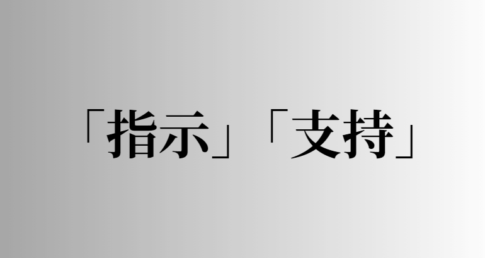
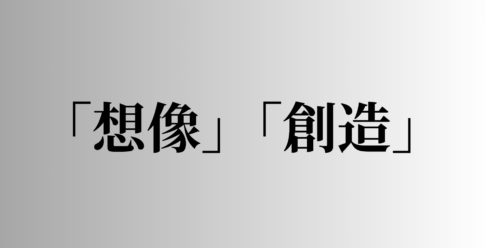

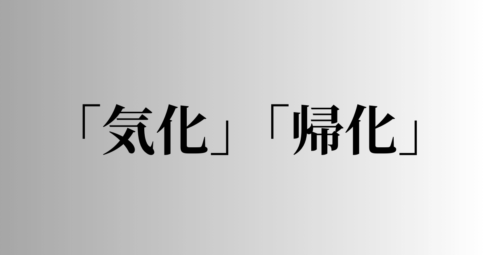

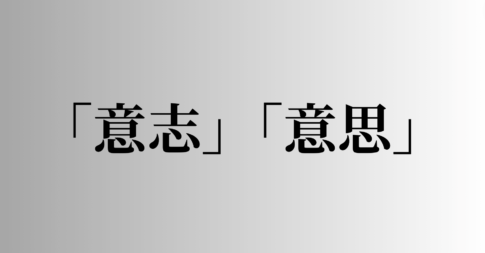
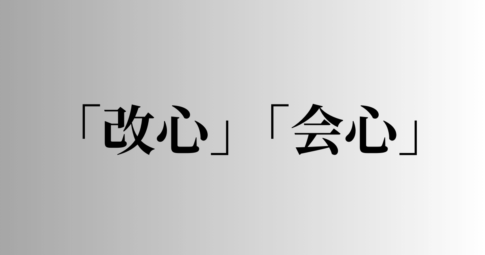
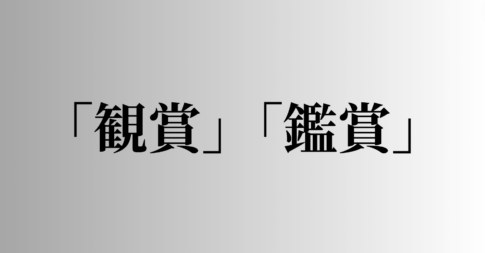
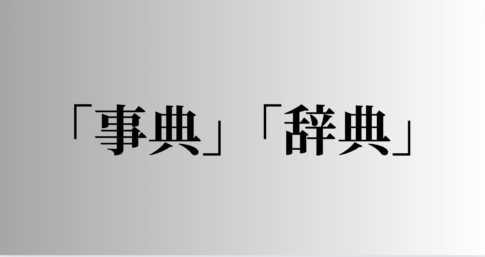

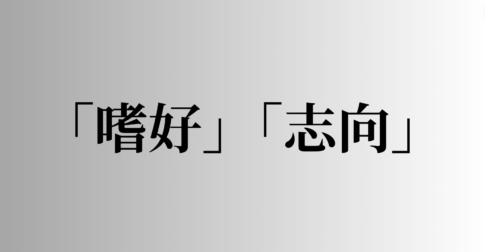
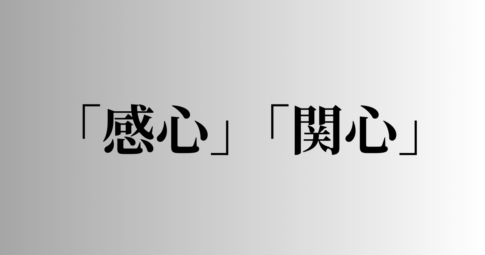
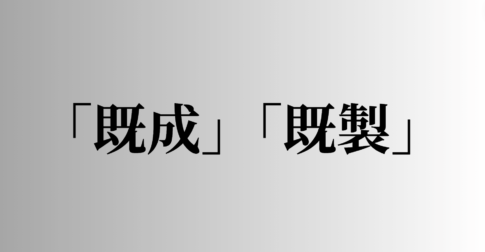
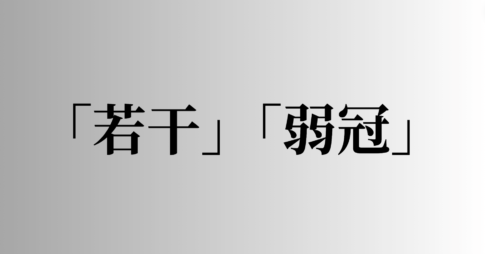
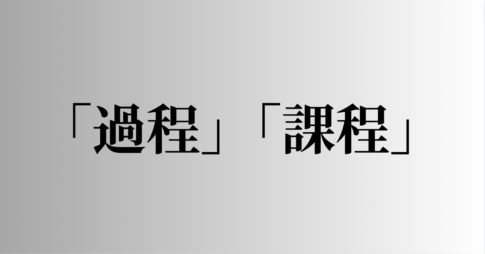
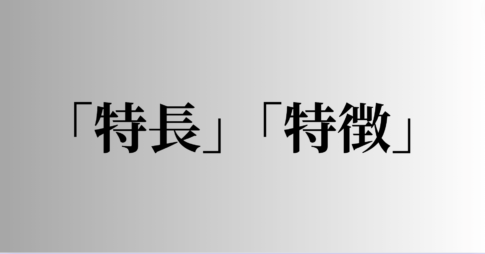


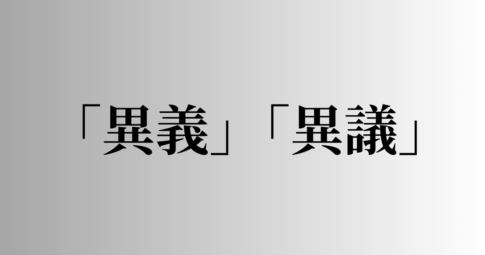
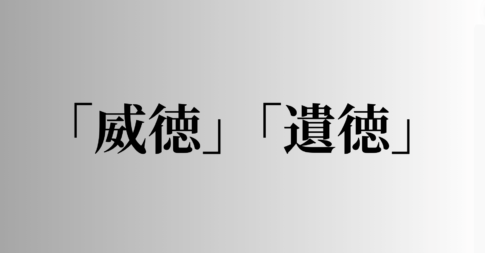


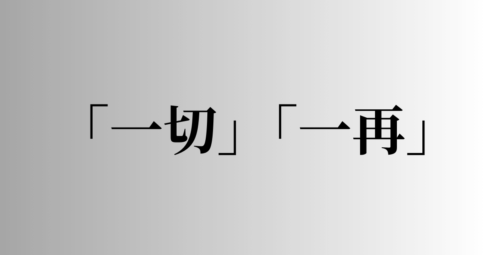
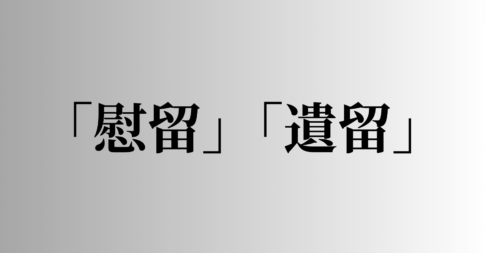

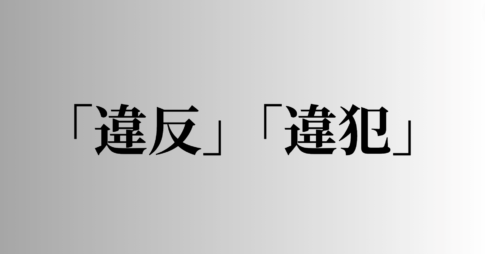
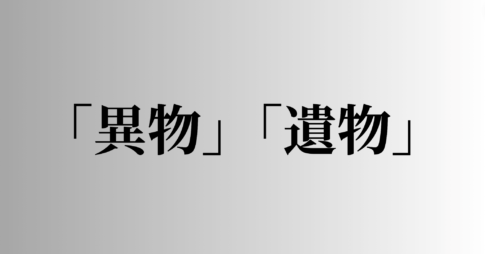
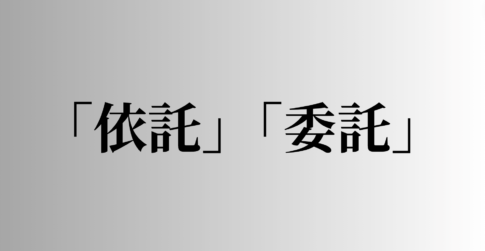
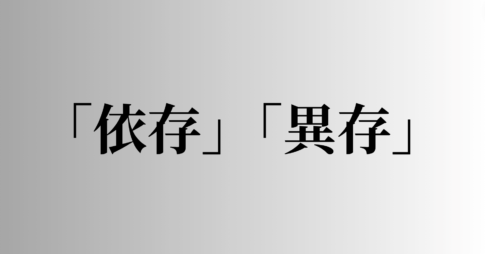
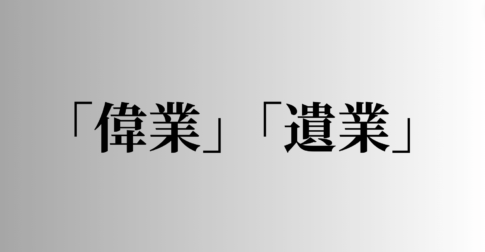

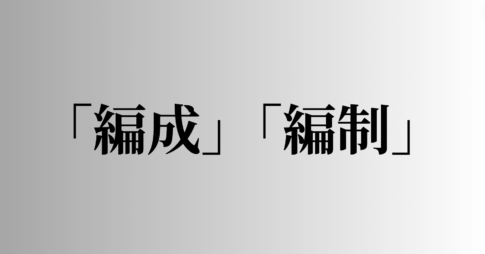
コメントを残す